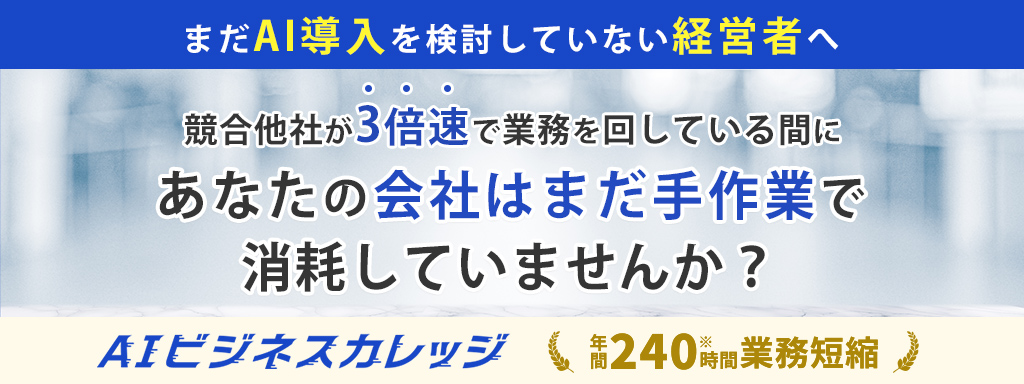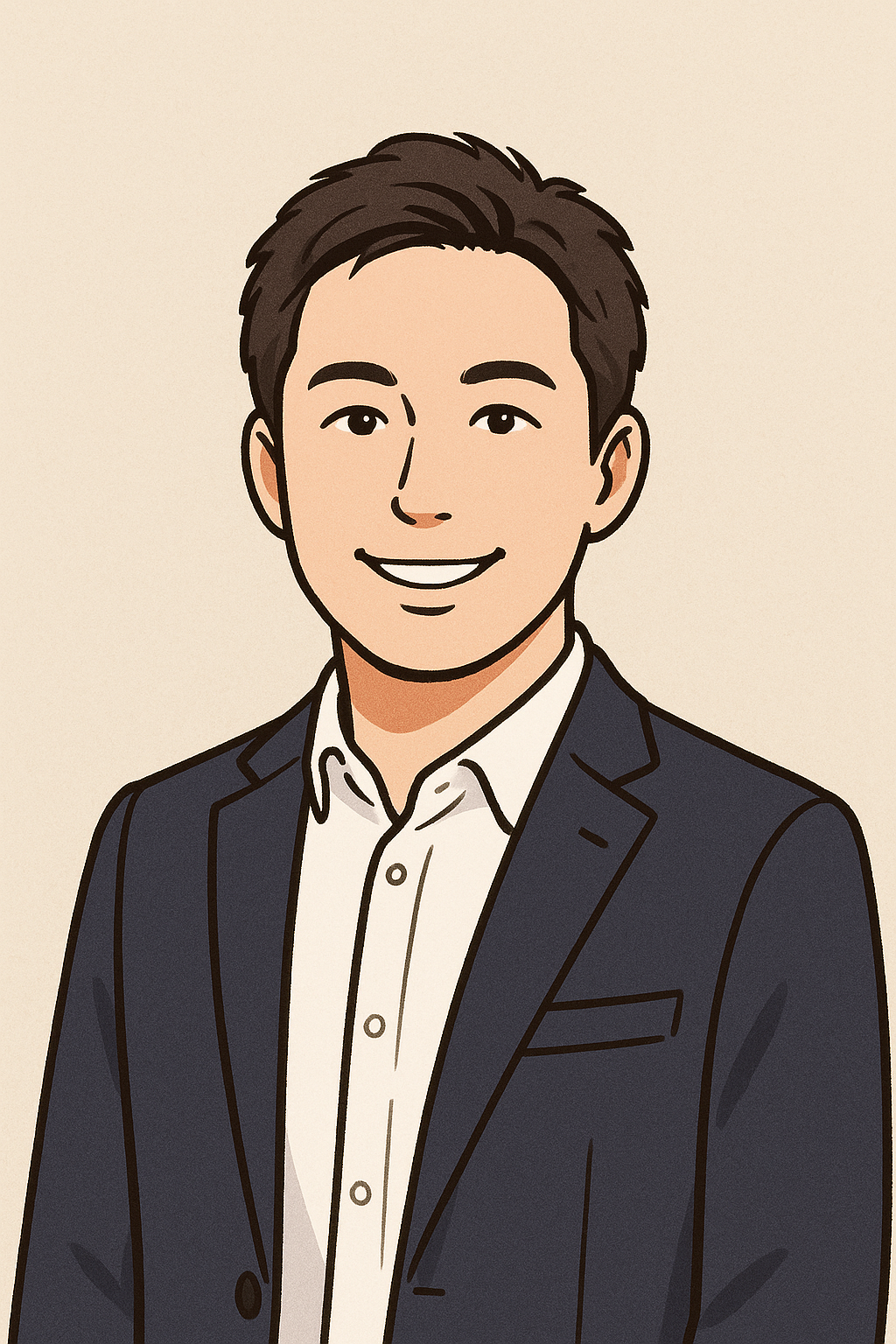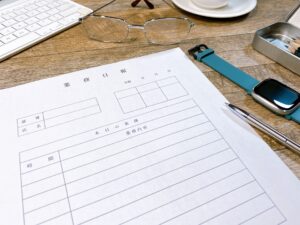「全社でDXを推進したいが、社員のITスキルが追いつかない」「高価なツールを導入したものの、結局一部の社員しか使っていない」といった課題を抱えていませんか。
社内のデジタル化が思うように進まない根本的な原因は、多くの場合、ツールやシステムではなく「人材」にあります。この記事では、その解決策として「DX教育」から始める社内デジタル化支援こそが成功の鍵であると結論づけています。本記事を読めば、DX推進の土台となる人材育成から始め、デジタルツールを全社に定着させるまでの具体的な5つのステップが明確にわかります。さらに、自社の課題に最適な支援サービスの選び方から、国内外の成功事例までを網羅的に解説。掛け声だけで終わらない、成果に繋がるDX推進の具体的な道筋を描くための、実践的な知識がすべて手に入ります。
なぜ社内デジタル化の成功にDX教育が不可欠なのか

多くの企業が「社内デジタル化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性を認識し、様々なツール導入やシステム刷新に取り組んでいます。しかし、高価なツールを導入したにもかかわらず、「期待した効果が出ない」「一部の社員しか使っていない」といった課題に直面するケースは少なくありません。その根本的な原因は、多くの場合「人」と「組織」にあります。社内デジタル化を真に成功させるためには、ツールという「手段」の前に、それを使いこなす「人」を育てるDX教育が不可欠なのです。
この章では、なぜDX教育が成功の鍵を握るのか、その理由を深掘りしていきます。
DXが進まない本当の理由
最新のITツールを導入すれば、自動的に業務が効率化され、生産性が向上すると考えがちです。しかし、実際には多くの企業でDXが停滞しています。その背景には、テクノロジー以前の、組織に根ざした複数の課題が存在します。
理由1:目的の欠如と経営層の理解不足
DXが「ツール導入」そのものになってしまい、「何のためにデジタル化するのか」という本来の目的が経営層から現場社員まで共有されていないケースです。経営層がDXを単なるコスト削減や業務効率化の手段としか捉えていない場合、全社的な変革への強いコミットメントが得られず、取り組みが中途半端に終わってしまいます。
理由2:社員のスキル不足とITアレルギー
デジタルツールを使いこなすための基本的なITリテラシーやスキルが不足している状態です。特に、長年慣れ親しんだ業務プロセスを変えることへの抵抗感や、「新しいことは覚えたくない」といった心理的な壁(ITアレルギー)は、デジタル化の大きな障壁となります。結果として、導入されたツールは一部のITに詳しい社員しか使わない「宝の持ち腐れ」となってしまいます。
理由3:変化を拒む組織文化と抵抗勢力
「前例がない」「今までこのやり方で問題なかった」といった、変化を拒む企業文化もDXを阻害する大きな要因です。新しい取り組みに対して非協力的な部署や、変化による自身の役割喪失を恐れる管理職などが「抵抗勢力」となり、全社的な協力を得ることが難しくなります。
理由4:部署間の連携不足(サイロ化)
部署ごとに異なるシステムを導入し、データが分断されている「サイロ化」の状態も深刻な問題です。各部署が自身の業務の最適化のみを考えてしまい、全社横断でのデータ活用や業務プロセスの見直しが進まないため、DXがもたらす本来の効果を最大化できません。
DX教育がもたらす組織へのメリット
DX教育は、単にツールの使い方を教えるだけではありません。前述したDXが進まない根本的な理由を解消し、組織全体をデジタル化に適応した強い体質へと変革させる力を持っています。具体的には、以下のような多岐にわたるメリットが期待できます。
| メリットの対象 | 具体的な内容 | 組織にもたらす効果 |
|---|---|---|
| 意識・マインドセット | 全社員がDXの目的と重要性を理解し、「自分ごと」として捉えるようになります。デジタル技術を活用して自社の課題を解決しようという主体性が生まれます。 | 変化を前向きに捉える組織文化が醸成され、DX推進への心理的障壁が低減します。 |
| スキル・リテラシー | 基本的なITスキルからデータ分析、セキュリティ知識まで、全社的なデジタルリテラシーが底上げされます。これにより、導入されたツールが形骸化せず、現場で能動的に活用されるようになります。 | 業務効率や生産性が飛躍的に向上し、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。 |
| 人材育成 | 専門部署だけでなく、各事業部門にもDXを牽引できるリーダーが育ちます。現場の課題を深く理解した人材がDXを推進することで、より実効性の高い施策が実現します。 | 外部のコンサルタントやITベンダーに依存しない、自走可能なDX推進体制が構築されます。 |
| 組織文化の変革 | 部署の垣根を越えて知識やデータを共有し、協力し合う文化が根付きます。失敗を恐れずに新しい挑戦を推奨する風土が生まれ、イノベーションが創出しやすい環境が整います。 | 組織全体の競争力が強化され、市場の変化に迅速に対応できるアジャイルな経営が実現します。 |
このように、DX教育は社内デジタル化を成功に導くための土台作りそのものです。ツールという「点」の投資だけでなく、教育という「人」への投資を並行して行うことこそが、持続的な成長を実現する唯一の道筋と言えるでしょう。
社内デジタル化支援を成功させる5つのステップ
社内のデジタル化は、単に新しいツールを導入するだけでは成功しません。社員一人ひとりがデジタル技術を理解し、主体的に活用できる環境を整える「DX教育」が不可欠です。ここでは、DX教育を起点として社内デジタル化を成功に導くための、具体的かつ実践的な5つのステップを詳しく解説します。このステップを着実に実行することで、組織全体のDXリテラシーが向上し、持続的な成長基盤を構築できるでしょう。
ステップ1 現状把握と明確な目標設定
DX推進の第一歩は、自社の「現在地」を正確に把握し、目指すべき「目的地」を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、教育もツール導入も効果が半減してしまいます。まずは客観的なデータに基づき、現状と課題を洗い出すことから始めましょう。
社員のITリテラシーを可視化する
社内デジタル化の主役は社員です。そのため、まずは社員全体のITリテラシーレベルを正確に把握することが重要です。これにより、全社一律の研修ではなく、個々のレベルに合わせた効果的な教育プログラムを設計できます。具体的な可視化の方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- スキルマップの作成: 職種や役職ごとに求められるデジタルスキルを定義し、各社員がどのレベルにあるかを自己申告や上長評価でマッピングします。
- ITリテラシー診断テストの実施: Officeソフトの操作スキル、情報セキュリティに関する知識、クラウドサービスの利用経験などを測るテストを実施し、組織全体の強みと弱みを定量的に把握します。
- アンケート調査: デジタルツールに対する意識や、日常業務で感じている課題などをヒアリングし、潜在的なニーズや抵抗感を把握します。
これらの手法で得られたデータは、後の教育計画策定における貴重な判断材料となります。
経営課題からDXのゴールを決める
DXはそれ自体が目的ではなく、あくまで経営課題を解決するための手段です。したがって、デジタル化のゴールは、必ず経営課題と結びついている必要があります。「生産性を15%向上させる」「新規顧客獲得コストを20%削減する」「顧客満足度を10%向上させる」といった、具体的で測定可能な目標(KGI: Key Goal Indicator)を設定しましょう。
ゴール設定のプロセスでは、経営層や各部門の責任者へのヒアリングが欠かせません。トップダウンの視点(経営戦略)とボトムアップの視点(現場の課題)をすり合わせることで、全社が納得感を持って取り組める、実効性の高いゴールが設定できます。
ステップ2 全社的なDX教育計画の策定
現状とゴールが明確になったら、次はそのギャップを埋めるための具体的な教育計画を策定します。誰に、何を、どのように教えるのかを定義し、DXを推進するための組織体制を構築するフェーズです。
対象者別の教育カリキュラム設計
社員の役職や職務によって、求められるDXの知識やスキルは異なります。そのため、対象者別に最適化されたカリキュラムを設計することが、教育効果を最大化する鍵となります。画一的な研修ではなく、それぞれの役割に応じた内容を提供しましょう。
| 対象者 | 教育の目的 | カリキュラム内容の例 |
|---|---|---|
| 経営層 | DXの戦略的重要性の理解と、投資判断能力の向上 | 最新技術動向、DX成功企業の事例研究、データドリブン経営、DX関連法規 |
| 管理職 | 部下のDX推進をリードし、業務プロセスの変革を主導する能力の習得 | プロジェクトマネジメント、業務改善手法、データ分析の基礎、部下へのコーチング |
| 一般社員 | デジタルツールを使いこなし、日常業務の効率化を実現するスキルの習得 | Office 365やGoogle Workspaceの応用、コミュニケーションツール(Slack, Teams)活用術、情報セキュリティ基礎、RPAツールの基本操作 |
| IT部門 | 全社のDXを技術面から支え、新たな価値創造を牽引する専門知識の深化 | クラウドアーキテクチャ、AI・機械学習の基礎、サイバーセキュリティ対策、アジャイル開発手法 |
DX推進体制の構築
DX教育と社内デジタル化を円滑に進めるためには、専門の推進体制が不可欠です。多くの場合、情報システム部門だけでは全社的な変革を主導するのは困難です。経営企画、人事、そして各事業部門を巻き込んだ、横断的なチームを組成しましょう。
このチームが中心となり、DX戦略の策定、教育計画の実行、各部署との調整、進捗管理などを担います。特に重要なのは、経営層がこの体制に強くコミットし、必要な権限とリソースを与えることです。また、各部署からデジタル化に意欲的なキーパーソンを選出し、現場のリーダーとして育成することも、変革をスムーズに進める上で効果的です。これにより、トップダウンの指示とボトムアップの活動が連動し、全社的なムーブメントが生まれます。
ステップ3 DX教育プログラムの選定と実行
策定した計画に基づき、いよいよ教育プログラムを実行に移します。ここでは、多様な学習スタイルに対応し、かつ学んだ知識が実際の業務に活かされるような「実践」を重視したプログラムを選ぶことが重要です。
eラーニングと集合研修の使い分け
DX教育には、時間や場所を選ばずに学べるeラーニングと、講師や他の受講者と対話しながら深く学べる集合研修があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的応じて効果的に使い分ける「ブレンディッドラーニング」が推奨されます。
| eラーニング | 集合研修(対面・オンライン) | |
|---|---|---|
| メリット | ・時間や場所の制約が少ない ・繰り返し学習が可能 ・大人数に一斉提供でき、コストを抑えやすい | ・双方向のコミュニケーションが可能 ・実践的な演習(ワークショップ)がしやすい ・受講者同士のネットワーキングが生まれる |
| デメリット | ・モチベーション維持が難しい ・実践的なスキルの習得には不向きな場合がある ・疑問点をその場で解消しにくい | ・時間や場所の調整が必要 ・一人あたりのコストが高くなりやすい ・日程が合わないと参加できない |
| 適した内容 | ITパスポートなどの資格取得に向けた基礎知識のインプット、情報セキュリティのルール周知 | 特定のツールを使った業務改善ワークショップ、デザインシンキング、データ分析演習 |
例えば、基礎的な知識やツールの操作方法はeラーニングで各自が習得し、その知識を応用して自社の課題解決策を議論するワークショップを集合研修で実施する、といった組み合わせが効果的です。
実践を促すアウトプットの機会
研修で学んだ知識は、使わなければすぐに忘れてしまいます。「知っている」状態から「できる」状態へと転換させるためには、学習内容を実際の業務で活用するアウトプットの機会を意図的に設けることが不可欠です。
- 業務改善コンテストの開催: 学んだ知識やツールを活用して、自身の業務を改善するアイデアを募集し、優れた提案を表彰します。
- OJTとの連携: 研修で学んだ内容を、上司や先輩のサポートのもとで実際の業務(OJT: On-the-Job Training)に活かす機会を作ります。
- 社内プロジェクトへの参加: 部門横断のDXプロジェクトに参加する機会を提供し、より高度で実践的な経験を積ませます。
こうしたアウトプットの場は、社員の成功体験につながり、さらなる学習意欲やデジタル化への主体的な参加を促す好循環を生み出します。
ステップ4 学習と並行したデジタルツールの導入支援
DX教育とツールの導入は、車の両輪です。教育で社員のITリテラシーが向上しても、それを活かすためのツールがなければ業務は変わりません。逆に、優れたツールを導入しても、使いこなせる社員がいなければ宝の持ち腐れです。両者を並行して進めることが成功の鍵です。
業務プロセスに合わせたツール選定
デジタルツールを選定する際は、知名度や機能の多さだけで判断してはいけません。最も重要なのは、「自社の経営課題や業務プロセスに合っているか」という視点です。まずは既存の業務フローを可視化し、どこにボトルネックがあるのか、どの部分をデジタル化すれば最も効果が高いのかを分析します。
その上で、現場の担当者も交えて複数のツールを比較検討し、無料トライアルなどを活用して実際の使用感を確かめることが重要です。例えば、営業部門の生産性向上が課題であればSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)、経理部門の定型業務削減が課題であれば会計ソフトやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などが候補となるでしょう。
導入後の定着を支援する仕組み
新しいツールは、導入して終わりではありません。社員がスムーズに利用を開始し、日常業務に定着させるための支援が不可欠です。導入後の混乱を最小限に抑え、活用を促進するために、以下のような仕組みを整えましょう。
- ヘルプデスクの設置: 操作方法がわからない、トラブルが発生したといった際に、気軽に相談できる窓口を設けます。
- マニュアルやFAQの整備: 分かりやすい操作マニュアルや、よくある質問とその回答(FAQ)を準備し、いつでも参照できるようにします。
- 定期的な勉強会や活用事例共有会の開催: ツールの便利な使い方を紹介したり、うまく活用している社員の事例を共有したりする場を設け、利用を促進します。
- 利用状況のモニタリング: ツールの利用率などを定期的にチェックし、活用が進んでいない部署や社員には個別にフォローアップを行います。
ステップ5 効果測定と継続的な改善
DXの取り組みは一度で完了するものではありません。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回し続け、継続的に取り組みを改善していくことが重要です。そのために、客観的な指標に基づいた効果測定の仕組みが不可欠となります。
KPI設定と定期的なレビュー
ステップ1で設定した最終目標(KGI)の達成度を測るため、プロセスごとの具体的な目標値であるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。KPIは、取り組みの進捗状況を客観的に把握し、問題点を早期に発見するための重要な指標です。
設定すべきKPIの例としては、以下のようなものが考えられます。
- 教育に関するKPI: 研修受講率、理解度テストの平均点、資格取得者数、従業員満足度アンケートのスコア
- ツール導入に関するKPI: 対象ツールの利用率(ログイン率)、特定業務の処理時間削減率、ペーパーレス化率
- 成果に関するKPI: 一人当たりの生産性、残業時間の削減率、コスト削減額
これらのKPIを定期的(月次や四半期ごと)にレビューし、目標達成に向けて計画通りに進んでいるかを確認します。遅れが見られる場合は、その原因を分析し、速やかに改善策を講じましょう。
社員からのフィードバック活用
定量的なKPIデータだけでなく、現場で働く社員からの定性的なフィードバックも、取り組みを改善するための貴重な情報源です。実施した研修プログラムや導入したツールについて、定期的にアンケートやヒアリングを行い、現場の生の声を集めましょう。
「研修内容が実務と合っていなかった」「ツールのこの機能が使いにくい」といった具体的な意見は、次の改善アクションに直結します。フィードバックを真摯に受け止め、改善に活かす姿勢を示すことは、社員の当事者意識を高め、全社的な協力体制を築く上でも非常に重要です。このサイクルを回し続けることで、社内デジタル化の取り組みは、より自社に最適化された実効性の高いものへと進化していきます。
DX教育と社内デジタル化支援サービスの選び方

DX教育と社内デジタル化支援を成功させるには、自社の状況に最適なサービスパートナーを選ぶことが極めて重要です。しかし、市場には多種多様なサービスが存在し、どのベンダーを選べば良いか迷ってしまう担当者の方も少なくありません。ここでは、自社のDXを真に成功へ導くパートナーを見極めるための、3つの重要な選定ポイントを具体的に解説します。これらの視点を持ってサービスを比較検討することで、投資対効果の高い支援を得られる可能性が格段に高まります。
自社の課題に合った支援範囲か
DX支援サービスと一言でいっても、その提供範囲はベンダーによって大きく異なります。戦略策定のような上流工程に特化したコンサルティングファームもあれば、特定のツール導入や技術研修に強みを持つ企業もあります。まず行うべきは、自社がDX推進のどのフェーズにあり、どのような課題を抱えているのかを明確にすることです。その上で、課題解決に直結する支援を提供してくれるサービスを選びましょう。
例えば、以下のように自社の課題と必要な支援範囲を整理することで、選ぶべきサービスが明確になります。
| 企業の主な課題 | 対応する支援サービスの範囲(例) |
|---|---|
| DXの方向性が定まらず、何から手をつければ良いかわからない | DX戦略策定支援、現状アセスメント、ロードマップ作成、経営層向けワークショップ |
| 社員全体のITリテラシーが低く、デジタルツールへの抵抗感が強い | 全社向けITリテラシー研修、DXマインド醸成研修、階層別・職種別eラーニングプログラムの提供 |
| 特定の業務(例:経費精算、顧客管理)を効率化したい | 業務プロセス分析、RPAやSFA/CRMといった特定ツールの選定・導入・定着支援 |
| DXを推進する専門人材が社内にいない | DX推進リーダー育成プログラム、データサイエンティスト育成研修、外部人材によるOJT支援 |
サービス選定の際には、提案された支援内容が自社の課題と合致しているかはもちろん、「どこからどこまで」を支援のスコープ(範囲)としているのかを契約前に詳細に確認することが不可欠です。期待していた支援が範囲外だった、という事態を避けるためにも、複数のベンダーから提案を受け、支援範囲を比較検討することをおすすめします。
伴走型のサポート体制があるか
DXは、一度研修を実施したりツールを導入したりすれば完了するものではありません。社員が新たな知識やツールを実務で活用し、それが組織文化として定着するまでには時間がかかります。そのため、単発の研修やコンサルティングだけでなく、プロジェクトの進行に合わせて継続的にサポートしてくれる「伴走型」の支援体制があるかどうかは非常に重要な選定基準です。
優れた伴走型支援パートナーは、以下のようなサポートを提供してくれます。
- 定期的な進捗確認と課題解決のミーティング: 計画通りに進んでいるかを確認し、新たに出てきた課題に対して共に解決策を検討します。
- チャットツールなどによる随時相談窓口: 現場で発生した小さな疑問やトラブルに対し、迅速に回答やアドバイスを提供します。
- 現場へのヒアリングと改善提案: 実際にツールを利用する従業員の声を聞き、より効果的な活用方法やプロセスの改善を提案します。
- DX推進担当者へのメンタリング: 社内の推進担当者が孤独に陥らないよう、専門的な知見からアドバイスを行い、精神的な支えとなります。
「研修を納品して終わり」ではなく、組織が自走できるようになるまで長期的な視点で寄り添い、共に汗を流してくれるパートナーを選びましょう。契約形態がプロジェクト単位なのか、あるいは月額リテナー契約で継続的な支援が可能なのかも確認しておくと良いでしょう。
豊富な実績と成功事例
サービス提供企業のウェブサイトなどで公開されている実績や導入事例は、その実力を測るための客観的な指標となります。特に、自社と同じ業界や同程度の企業規模での支援実績が豊富かどうかは必ず確認すべきポイントです。
実績を確認する際は、以下の点に注目しましょう。
- 業界・業種への理解度: 例えば製造業と小売業では、業務プロセスや解決すべき課題が全く異なります。自社の業界特有の課題を深く理解し、的確なソリューションを提供できる知見があるかを確認します。
- 企業規模との適合性: 大企業の全社的な組織変革と、中小企業の限られたリソース内での業務効率化では、求められる支援の進め方が異なります。自社と近い規模の企業を成功に導いた実績があるかは、重要な判断材料です。
- 成功事例の具体性: 「生産性が向上しました」といった抽象的な成果だけでなく、「どのような課題に対し」「どのような教育やツール導入を行い」「結果として、〇〇の業務時間が月間で〇〇時間削減された」というように、プロセスと定量的な成果が具体的に示されているかを確認します。定性的な成果(社員のDXへの意識向上など)についても言及があれば、より信頼性が高まります。
可能であれば、商談の際に具体的な事例について担当者から直接話を聞く機会を設けましょう。その際の受け答えの的確さや熱意も、信頼できるパートナーかどうかを見極める上で参考になります。
【事例紹介】DX教育で社内デジタル化に成功した企業
DX教育とデジタル化支援を組み合わせることで、多くの企業が課題を乗り越え、大きな成果を上げています。ここでは、企業の規模別に、具体的な成功事例を2つご紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、成功のヒントを見つけてください。
中小企業の業務効率化事例
従業員約70名の老舗部品メーカーA社は、長年の紙とFAXを中心としたアナログな業務フローが常態化し、生産性の低下や若手社員の定着率の低さに悩んでいました。特に、受発注管理や日報作成の非効率さが大きな課題でした。
そこで同社は、全社員を対象としたDX教育から着手。まずはPCの基本操作やクラウドサービスの概念といったITリテラシーの底上げを図る研修を実施しました。次に、各部門から選抜されたメンバーでDX推進チームを結成し、業務改善に直結するクラウド型業務改善ツール(kintoneなど)の集中研修と導入支援サービスを並行して活用しました。
経営層も研修に積極的に参加し、「デジタル化は会社が生き残るために不可欠」というメッセージを発信し続けたことで、当初は抵抗感のあったベテラン社員も徐々に協力的になりました。結果として、アナログ業務からの脱却に成功し、組織全体の生産性向上を実現しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 抱えていた課題 |
|
| 実施したDX教育と支援 |
|
| 得られた成果 |
|
大企業の組織文化変革事例
国内大手の総合商社B社は、事業部ごとの縦割り意識が強く、データが各所に散在する「サイロ化」が深刻な経営課題でした。市場の変化に対応した迅速な意思決定ができず、イノベーションが停滞していることに強い危機感を抱いていました。
同社が取り組んだのは、単なるツール導入ではなく、データドリブンな組織文化への変革を目指した全社的なDX教育プログラムです。経営層には「DX戦略とリーダーシップ」、管理職には「データに基づくマネジメント」、一般社員には「BIツールを活用したデータ分析基礎」といった階層別のカリキュラムを設計・実行しました。
教育と並行して、全社共通のデータ分析基盤(BIツール)を導入し、各部門に配置されたDXアンバサダーが現場での活用を支援する体制を構築。さらに、業務改善アイデアを競う社内コンテストを開催し、優れた提案には予算を付けて実行させるなど、学習したスキルを実践する機会を意図的に創出しました。
この取り組みにより、B社は部門の壁を越えたデータ活用を推進。経験や勘だけに頼らない、客観的なデータに基づいた意思決定が浸透し、新たなビジネスチャンスの創出へと繋がっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 抱えていた課題 |
|
| 実施したDX教育と支援 |
|
| 得られた成果 |
|
まとめ
本記事では、社内のデジタル化を成功に導く鍵として「DX教育」の重要性と、その具体的な進め方について5つのステップに沿って解説しました。多くの企業でDXが進まない本当の理由は、ツールの不足ではなく、社員のITリテラシーやデジタル技術に対するマインドセットにあります。DX教育は、こうした課題を根本から解決し、全社員が主体的にデジタル化を推進する組織文化を醸成するための不可欠な投資です。
成功への道筋としてご紹介した5つのステップ(①現状把握と目標設定、②教育計画の策定、③プログラムの実行、④デジタルツールの導入支援、⑤効果測定と改善)は、場当たり的な施策ではなく、戦略的にデジタル化を進めるための羅針盤となります。特に、社員のスキルレベルを可視化し、経営課題に直結したゴールを設定することが、DX推進の成否を分ける重要なポイントです。
また、自社だけで推進するのが難しい場合は、外部の専門的な支援サービスを活用することも有効な選択肢です。その際は、自社の課題に合った支援範囲か、伴走型のサポート体制が整っているか、そして豊富な実績があるかといった視点で慎重に選ぶことが求められます。
社内のデジタル化は、単に新しいツールを導入することではありません。社員一人ひとりがデジタル技術を使いこなし、業務を改善していくという「人」と「組織文化」の変革そのものです。この記事を参考に、まずは自社のDX教育のあり方を見直すことから、競争力のある未来への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。